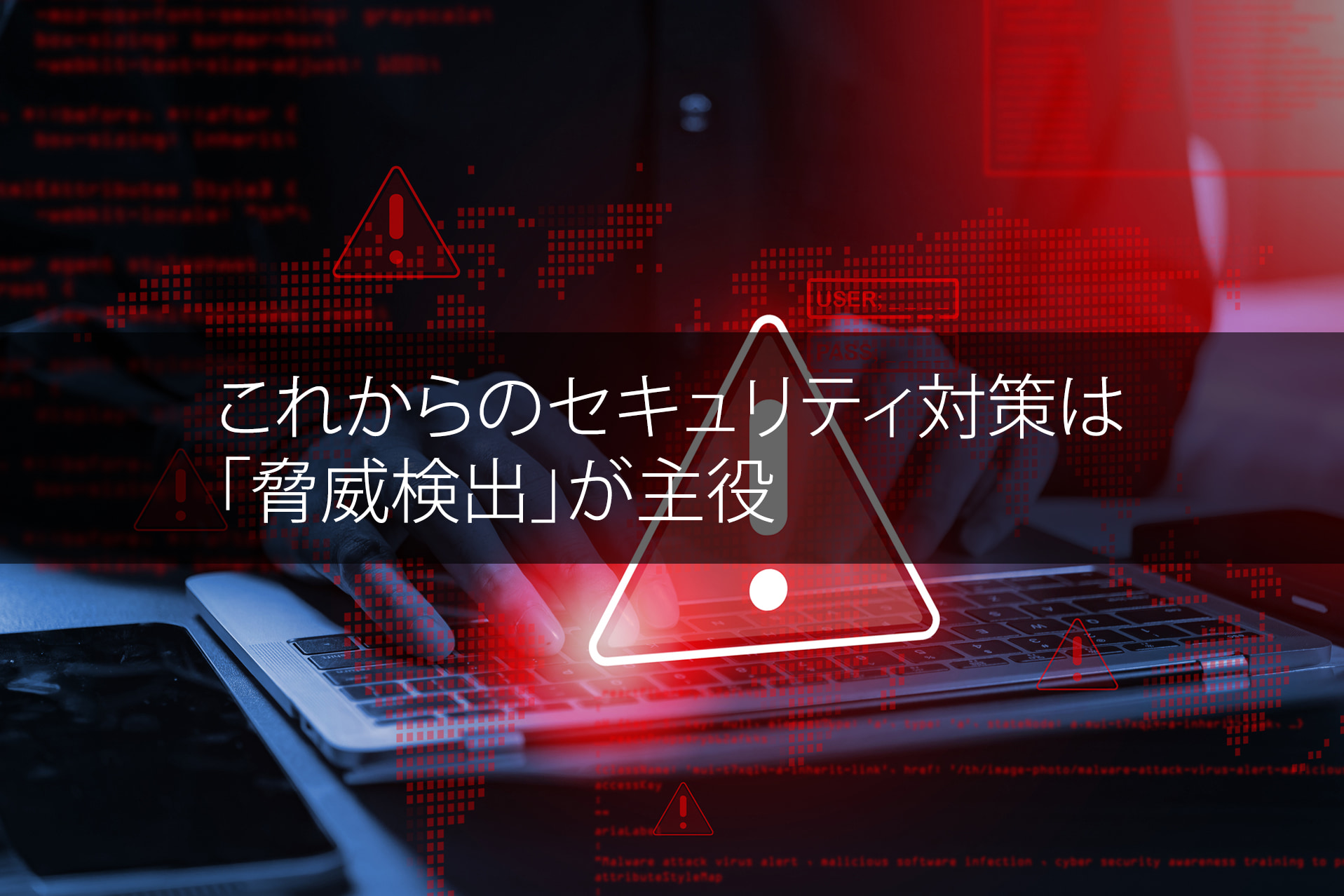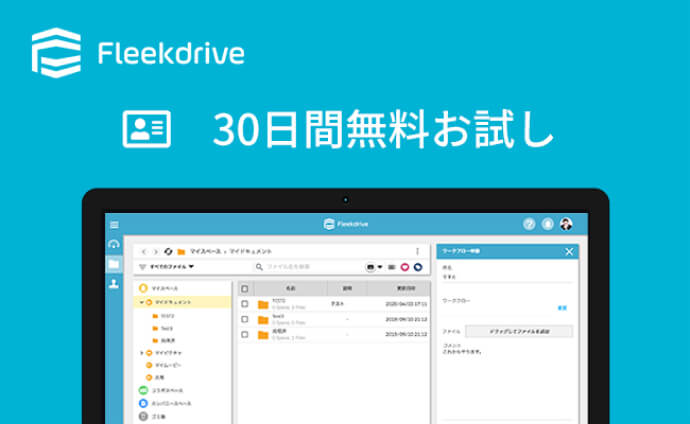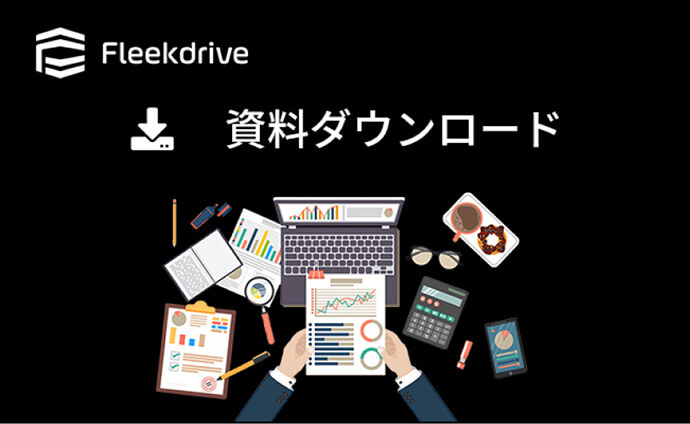「ファイアウォールも最新のものを使っているし、ウイルス対策ソフトも全PCに導入済み。うちのセキュリティは大丈夫だろう」。もし、そうお考えの情報システム部門ご担当者様がいらっしゃいましたら、今こそセキュリティ戦略の根本的な見直しが必要です。
テレワークの常態化やクラウド利用の拡大により、従来の境界型防御では十分なセキュリティを確保できません。今や「侵入は防ぎきれない」という前提に立ち、侵入後にいかに迅速に脅威を見つけ出すか、つまり「脅威検出」が事業継続の生命線です。
本記事では、主役となりつつある脅威検出に焦点を当て、その重要性から具体的な脅威検出の手法、そして未来までを解説します。効果的な脅威検出で、企業のセキュリティを新たなレベルへ引き上げましょう。
Contents
現代セキュリティの背景:なぜ脅威検出が重要なのか?
これまでも脅威を検知する仕組みは存在しましたが、なぜ今、その重要性が急速に高まっているのでしょうか。その背景には、企業を取り巻く環境の劇的な変化があります。
境界が消えたオフィス環境
かつてのセキュリティは、会社のネットワークという城をファイアウォールという城壁で守る境界型防御が中心でした。しかし、テレワークの普及により、従業員は自宅やカフェなど、城壁の外から業務を行うのが当たり前になりました。VPNで接続していても、利用されるPCがマルウェアに感染すれば、そこが侵入の起点となり得ます。もはや、安全な内側と危険な外側という明確な境界はありません。
クラウドシフトによるデータの分散
業務で利用するデータも、社内のファイルサーバーだけでなく、複数のクラウドサービス上に分散して保管されるようになりました。これは利便性を向上させる一方で、守るべき対象が広範囲に散らばっていることを意味します。情報システム部門が把握していないクラウドサービス(シャドーIT)が利用されていれば、そこがセキュリティホールになる可能性もあります。
前提となった「侵入されること」
ランサムウェア攻撃やサプライチェーン攻撃など、サイバー攻撃はますます高度化・巧妙化しています。攻撃者は正規のツールを悪用したり、脆弱性を巧みに突いたりして、静かにシステム内部へ侵入します。事実、多くの企業が侵入の事実に数ヶ月間も気づかないケースが報告されています。
このような状況下で注目されているのがゼロトラストという考え方です。これは「社内外のすべての通信を信頼せず、常に検証する」というアプローチであり、侵入を前提とした対策の根幹をなします。そして、そのゼロトラスト環境で「信頼できないもの=脅威」をあぶり出すのが脅威検出です。
セキュリティを強化する具体的な脅威検出のアプローチ
侵入を前提とした脅威検出は、単一のソリューションではなく、複数の仕組みを組み合わせた多層防御で実現します。ここでは、現在の主流となっている代表的なアプローチを3つご紹介します。
EDR (Endpoint Detection and Response)
EDRは、PCやサーバーといったエンドポイントを守るための監視システムのようなものです。従来のウイルス対策ソフトが既知のマルウェアの侵入を防ぐことに主眼を置くのに対し、EDRは侵入後の不審な挙動を検知・対応することに特化しています。
例えば、Wordファイルを開いた後に、裏で不審な通信を開始したり、OSの正規ツール(PowerShellなど)を悪用して他のファイルにアクセスしようとしたりする動きを捉えます。入口で防げなかったとしても、PC内で悪さを始めた瞬間に検知し、隔離・駆除するのがEDRの役割です。
NDR (Network Detection and Response)
NDRは、ネットワーク全体の交通監視システムに例えられます。社内ネットワークを行き交うすべての通信を監視し、異常なパターンを検出します。
特に、一度侵入した攻撃者が、他のサーバーやPCへ感染を広げようとする動き「ラテラルムーブメント(内部での横展開)」の検知に有効です。例えば、「通常は経理サーバーにしかアクセスしないはずのPCが、開発サーバーにアクセスしようとしている」といった異常な通信を検知し、警告を発します。EDRが個々のPCを守るのに対し、NDRは組織全体のネットワークを守る役割を担います。
SIEM/SOAR
SIEM(Security Information and Event Management)は、組織内の様々なセキュリティ機器(ファイアウォール、EDR、NDR、クラウドサービスのログなど)から集めた膨大なログ情報を一元的に分析する司令塔です。個々のログだけでは気づけない脅威の兆候も、複数のログを関連付けて分析することで、「AというPCで不審な挙動があり、その直後にBというサーバーへの異常な通信が発生した。これは高度な攻撃の可能性が高い」といったインテリジェントな検知が可能になります。
さらに、SIEMと連携するSOAR(Security Orchestration, Automation and Response)は、検知した脅威への初動対応を自動化する仕組みです。例えば、SIEMが脅威を検知したら、SOARが自動的に該当PCのネットワークを遮断したり、管理者に通知したりといった一連の対応手順を実行します。これにより、インシデント対応の迅速化と担当者の負荷軽減を実現します。
これらのソリューションを組み合わせ、より広範囲の脅威を検知・対応するXDR(Extended Detection and Response)という概念も登場しており、脅威検出はより統合的なアプローチへと進化しています。
失敗しない脅威検出導入とセキュリティ運用のポイント
これらの強力なソリューションも、ただ導入するだけでは効果を発揮しません。情報システム部門が主導して、押さえるべきポイントが3つあります。
1. 守るべき情報資産の棚卸しとリスク評価
まず、「自社にとって最も守るべきものは何か?」を明確にすることから始めます。顧客情報、技術情報、財務情報など、漏洩・改ざん・破壊された場合に事業に致命的な影響を与える情報資産をリストアップし、それらがどこに保管されているのかを把握します。その上で、想定される脅威と、それが発生した場合の影響度を評価します。このリスク評価の結果が、どの範囲に、どのレベルの脅威検出ソリューションを導入すべきかの判断基準となります。
2. 検知後の「運用体制」の構築
脅威検出ソリューションは、アラートを発することがゴールではありません。アラートが鳴ってからがスタートです。「誰が」「いつ」「どのように」対応するのか、具体的なインシデントレスポンス計画を策定し、訓練しておく必要があります。
24時間365日の監視体制を自社で構築するのは容易ではありません。そのため、近年ではEDRやNDRの運用を専門家に委託するMDR(Managed Detection and Response)サービスを活用する企業が増えています。自社のリソースと求めるセキュリティレベルを天秤にかけ、外部サービスの活用も積極的に検討しましょう。
3. スモールスタートと効果測定
いきなり全社的に大規模なソリューションを導入するのではなく、まずは守るべき優先順位の高いシステムや部署から試験的に導入するスモールスタートを推奨します。PoC(概念実証)を通じて、自社の環境でどの程度の脅威が検知されるのか、誤検知はどのくらい発生するのかを把握し、運用上の課題を洗い出します。その結果をもとに、本格展開の計画を練ることで、投資対効果の高い導入が可能になります。
未来のセキュリティ:「脅威検出」はAIでどう進化するのか
今後の脅威検出は、AIや機械学習の活用によって、さらに高度化していくと予測されます。
予測的・能動的な脅威ハンティングへ
これからの脅威検出は、アラートを待つ受動的なものから、システム内に潜む脅威の痕跡を積極的に探し出す脅威ハンティングへとシフトしていきます。AIは膨大なログデータから未知の攻撃パターンや微細な異常の兆候を自律的に学習し、「まだアラートは出ていないが、この挙動は将来的な攻撃の予兆である可能性が高い」といった予測的な分析を可能にします。
情シスに求められるスキルの変化
このような進化に伴い、情報システム部門に求められる役割も変化します。単なるツールの導入・運用管理者ではなく、AIが提示する脅威インテリジェンスを解釈し、それが自社のビジネスにどのようなリスクをもたらすのかを経営層に分かりやすく説明するスキルが重要になります。また、セキュリティ戦略を事業戦略と一体のものとして立案し、関連部署と連携しながら推進していく視点も不可欠となるでしょう。
まとめ:脅威検出で実現する次世代の企業セキュリティ
もはや、サイバー攻撃による侵入を完全に防ぐことはできません。この現実を受け入れた上で、いかに迅速に脅威を検出し、被害を最小限に抑えるか。この「検知と対応(Detection and Response)」こそが、現代のセキュリティ対策の核であり、事業継続を左右する重要な経営課題です。
脅威検出は、コストのかかる保険ではなく、企業の信頼と未来を守るための投資です。まずは自社の現状を把握し、どこにリスクが潜んでいるかを評価することから、第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。