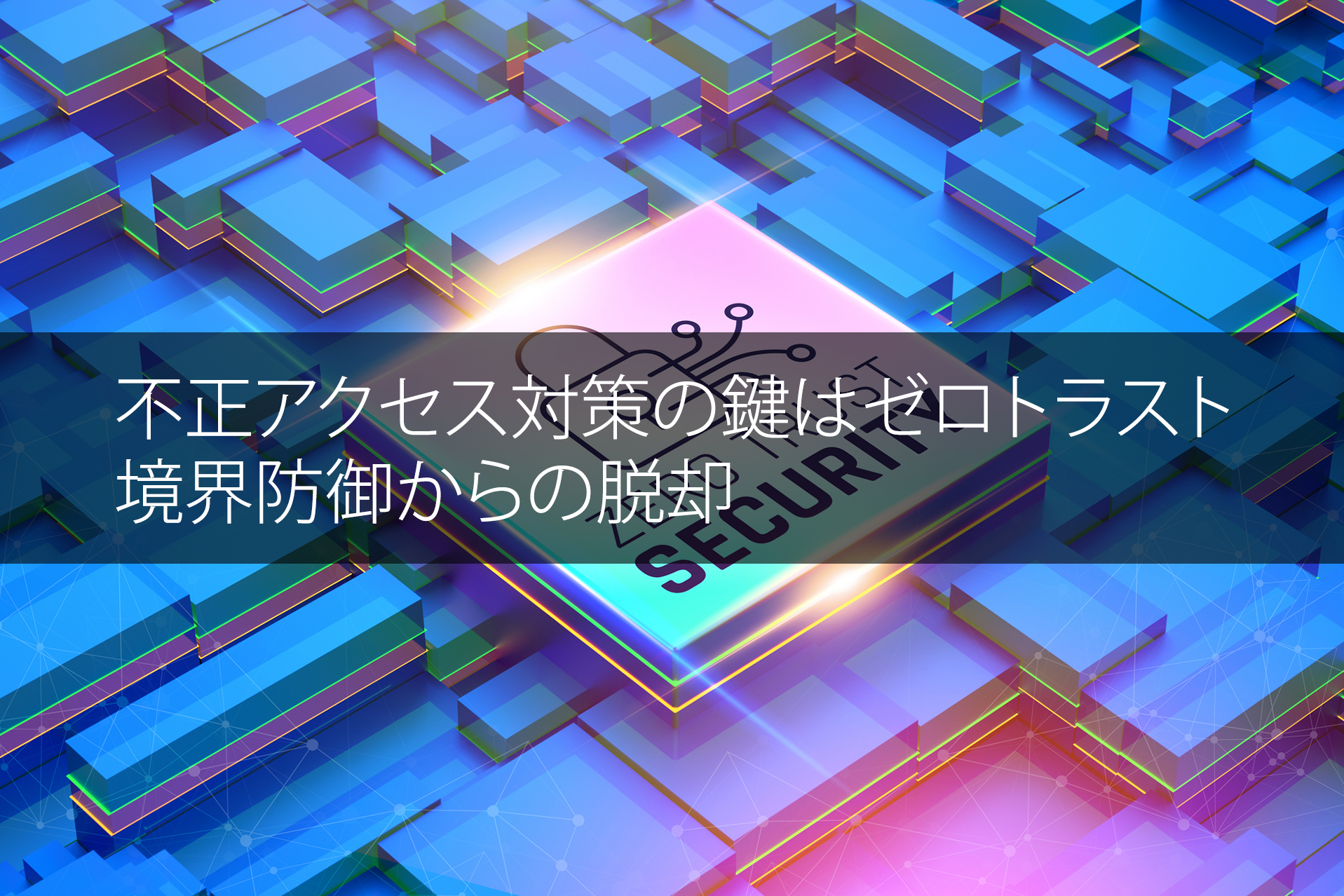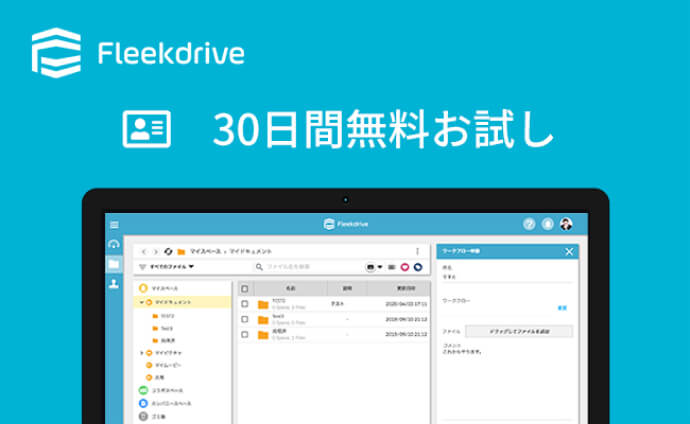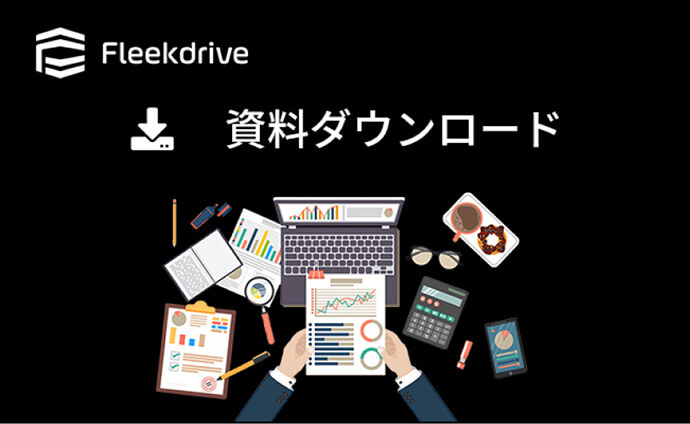テレワークの普及で、企業のファイル管理は境界型防御の外側に晒され、不正アクセスのリスクが急増しています。重要なのは外部からの不正アクセスだけでなく、内部の権限悪用まで見据えた対策を多層で設計すること。本記事では、ゼロトラストに基づく不正アクセス対策の具体手順を整理し、IPアドレス制限・多要素認証・監査ログを核にした対策の考え方と、法人向けのファイル共有セキュリティ構築の勘所を解説します。
Contents
従来の「境界型防御」が不正アクセス対策に機能しない理由
不正アクセス対策の基本であった「境界型防御」(ファイアウォールで外部と社内を分ける)は、テレワークとクラウドの普及により、その有効性を失いつつあります。
内部ネットワーク侵入後の「フリーパス」状態
不正アクセスは、必ずしも外部から直接サーバーを狙うとは限りません。従業員のPCがマルウェアに感染したり、VPNの脆弱性を突かれたりすることで、一度内部ネットワークに侵入されると、従来の境界型防御では、内部のファイルサーバーへのアクセス制御が不十分になり、情報漏洩やランサムウェア攻撃の被害が瞬時に拡大するリスクがあります。[出典: 経済産業省「サイバーセキュリティ経営ガイドライン Ver 3.0」
アクセス権限の悪用リスク
不正アクセスの脅威は外部からだけではありません。正規のアクセス権限を持つ従業員が、その権限を悪用して機密データを持ち出す内部不正も重大な情報漏洩リスクです。従来のファイル管理システムでは、アクセス権限を「参照」「編集」といった大まかな単位でしか設定できず、きめ細かなファイル共有セキュリティの統制が難しく、退職者などによる不正アクセスを許す温床となっていました。
ゼロトラスト原則に基づく不正アクセス対策の主要な手順
不正アクセス対策を抜本的に強化するには、「何も信頼しない」というゼロトラストの原則をファイル管理システムに適用し、予防、防御、そして検知といった多層的な手順を確立する必要があります。
Step 1: 予防と防御—最小権限と認証強化
不正アクセスを未然に防ぐためには、「アクセス権限管理の最小化」と「認証の多要素化」が核となります。
- 最小権限:業務に必要最小限の権限のみ。機密はDL/印刷を既定で禁止し、ワークフロー自動化で一時許可。
- IPアドレス制限:許可した拠点・VPNからのみ接続。
- 多要素認証(MFA):なりすましを抑止。
Step 2: 検知と追跡—監査ログで異常を可視化
不正アクセス対策において、防御をすり抜けた異常な行動を検知し、追跡する手順は不可欠です。法人向けファイル管理システムは、以下の条件で監査ログを取得し、管理者へアラートを発する必要があります。
- 異常検知:短時間の大量DL、普段と異なる端末/時間帯のログインなどを検知しアラート。
- 改ざん不能・長期保存:事後調査や監査に耐える証跡を保持。
Step 3: 権限移譲の自動化でリスクを低減
不正アクセスのリスクは、離職者や異動者のアクセス権限が放置されることからも発生します。人事情報システムと連携し、アカウントの無効化、アクセス権限の剥奪、ファイルの所有権移譲といった一連の手順をワークフロー自動化によって実行できる仕組みが、不正アクセス対策のリスクを継続的に低減することに繋がります。
不正アクセス対策は「信頼しないシステム」の構築から始まる
不正アクセス対策を成功させる鍵は、「社内だから安全」という従来の考え方を捨て、「誰も、何も、信頼しない」というゼロトラストの原則をファイル管理システムに適用することです。法人向けの高セキュリティなオンラインストレージを選定し、アクセス権限管理の最小化、IPアドレス制限、そして監査ログによる常時監視という多層的な対策手順を確立することが、情報漏洩リスクから企業を守るための最重要戦略となります。