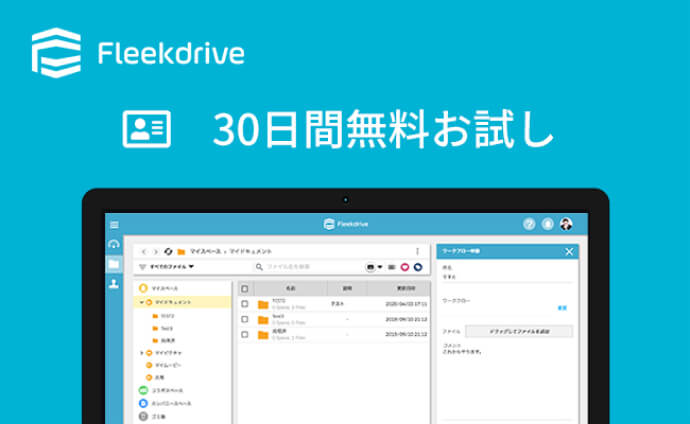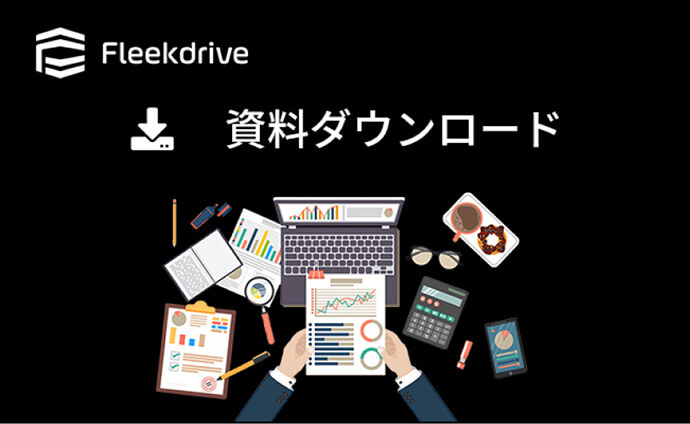近年、「ゼロトラスト」という言葉を耳にする機会が増えたのではないでしょうか。従来の境界型セキュリティが通用しなくなりつつある今、これは現代の企業セキュリティを考える上で避けては通れない重要な概念です。本記事では、ゼロトラストを理解し、日々の業務に活かすためのポイントを分かりやすく解説します。
なぜ今、ゼロトラストが企業に不可欠なのか?
かつて企業のセキュリティ対策は、「境界型防御」が主流でした。これは、社内ネットワークと社外ネットワークを明確に区切り、ファイアウォールなどで外部からの侵入を防ぎ、社内は安全な場所と見なす考え方です。しかし、この前提はもはや通用しません。
- クラウドサービスの普及とリモートワークの常態化: 業務で利用するアプリケーションやデータが社内サーバーだけでなく、クラウド上に分散するようになりました。また、コロナ禍を経てリモートワークが普及し、社員が社外から様々なデバイスを使って業務を行うのが当たり前になっています。これにより、「社内」と「社外」の境界線が曖昧になり、従来の防御策だけでは対応しきれなくなりました。
- サイバー攻撃の高度化・巧妙化: マルウェア、ランサムウェア、サプライチェーン攻撃、内部不正など、サイバー攻撃は日々進化し、その手口は非常に巧妙です。一度境界を突破されてしまえば、従来の防御では内部での横展開を止められないリスクが高まりました。
- 「信じない、常に検証する」の原則: 従来の境界型防御では、「一度社内に入れば安全」という前提がありました。しかし、ゼロトラストは「何も信頼しない(Zero Trust)」を前提とし、全てのアクセス要求を疑い、常に検証することで、セキュリティを強化するモデルです。たとえ社内からのアクセスであっても、安全性を確認するまで信頼しない、という考え方にシフトしています。
このような背景から、現代の複雑なIT環境と高度な脅威に対応するため、ゼロトラストの考え方が不可欠となっているのです。
ゼロトラストモデルに基づく具体的なセキュリティ対策
ゼロトラストは、単一の製品やソリューションではなく、複数の技術とポリシーを組み合わせた考え方であり戦略です。具体的な取り組みとしては、以下のような要素が挙げられます。
- 多要素認証(MFA)の徹底: パスワードだけでなく、スマートフォンアプリの認証コード、生体認証(指紋や顔)、ハードウェアトークンなど、複数の認証要素を組み合わせて本人確認を行います。これにより、パスワードが漏洩しても不正アクセスを防ぐ確率が高まります。
- デバイスの健全性チェック: ユーザーがアクセスに使用するPCやスマートフォンが、最新のセキュリティパッチが適用されているか、ウイルス対策ソフトが有効か、不正なソフトウェアがインストールされていないかなどを確認します。安全と判断されたデバイスからのアクセスのみを許可します。
- 最小権限の原則(Least Privilege): ユーザーやデバイス、アプリケーションには、業務上必要最低限のアクセス権限のみを付与します。これにより、万が一不正アクセスがあったとしても、被害範囲を最小限に抑えることができます。
- マイクロセグメンテーション: ネットワークを非常に細かく区切り、特定のアプリケーションやデータへのアクセスを厳密に制御します。例えるなら、オフィス全体を一つの部屋にするのではなく、部署ごと、さらには個人ごとに部屋を分け、必要な鍵(権限)を持つ人のみが入れるようにするイメージです。これにより、内部での横展開を防ぎます。
- 継続的な監視とログ分析: アクセスのログやシステムの状態を常に監視し、不審な挙動や異常をリアルタイムで検知します。AIや機械学習を活用した分析ツール(EDR、SIEMなど)を導入することで、人間の目では見つけにくい脅威も早期に発見し、迅速な対応につなげます。
- ネットワークアクセス制御(NAC)/ SDP(Software-Defined Perimeter): ユーザーやデバイス、アプリケーションの状況に応じて、動的にネットワークへのアクセスを制御します。必要な時だけ必要なリソースへのアクセスを許可し、それ以外の通信を遮断します。
これらの要素技術を組み合わせて、企業全体のセキュリティを段階的に強化していくのがゼロトラストのアプローチです。
導入を成功させるための実践的ポイント
ゼロトラストは壮大なテーマに見えますが、情報システム部として現実的に導入を進めるためのポイントがいくつかあります。
- 現状把握とロードマップ策定: まずは自社のIT資産(ユーザー、デバイス、アプリケーション、データ)や既存のセキュリティ対策、リスクを洗い出しましょう。その上で、どこから着手すべきか、どのようなステップでこのモデルへ移行していくかのロードマップを策定します。全ての要素を一度に導入しようとせず、優先順位を付けることが重要です。
- 関係部署との連携と理解促進: このモデルの導入はIT部門だけで完結するものではありません。経営層にはセキュリティ投資の重要性を説明し、予算とリソースの確保を依頼します。また、従業員に対しては、多要素認証の導入など、これまでの業務フローが変わる可能性があるため、丁寧に説明し、理解と協力を促すための教育や啓蒙活動が不可欠です。
- スモールスタートと段階的導入: 全てを一度に変えようとすると、現場の混乱やシステムトラブルの原因になりかねません。まずはリスクの高いシステムや少数のユーザーから導入を始め、効果を検証しながら徐々に適用範囲を広げていくスモールスタートが成功の鍵です。
- 継続的な運用と改善: このモデルは一度導入したら終わりではありません。脅威は常に変化するため、継続的な監視、ポリシーの見直し、システムの改善が不可欠です。定期的なセキュリティアセスメントや訓練を実施し、PDCAサイクルを回していくことが重要です。
- ツール選定と既存システムとの連携: このモデルを実現するためのツールは多岐にわたります。自社の環境や予算に合った適切なツールを選定し、既存のITインフラやアプリケーションとの連携性も考慮しましょう。複数のベンダーの製品を組み合わせる場合は、互換性や運用の一貫性も確認が必要です。
進化するセキュリティ対策と今後の展望
- SASE(Secure Access Service Edge)の普及: ネットワークとセキュリティ機能をクラウド上で統合し、どこからでも安全にアクセスできる環境を提供する「SASE」の普及が加速しています。これは、本モデルの概念を具体的に実現するアーキテクチャとして注目されており、セキュリティとネットワーク運用の効率化を両立させます。
- AI/機械学習による脅威検知・自動化の進化: AIや機械学習を活用した分析技術はさらに進化し、より高度な脅威を自動で検知し、対応を自動化する仕組みが発展していくでしょう。これにより、情報システム担当者の負担軽減にもつながります。
- OT/IoTセキュリティへの適用拡大: 工場設備(OT)やスマートデバイス(IoT)など、IT以外の領域にもこの考え方が広がっていくでしょう。これらのデバイスもネットワークに接続されることで攻撃対象となり得るため、厳格なアクセス制御が求められます。
- セキュリティはコストではなく投資へ: サイバー攻撃による企業への被害は甚大であり、セキュリティ対策はもはや単なるコストではなく、企業の事業継続と競争力を維持するための重要な「投資」であるという認識が、経営層の間でさらに高まっていくでしょう。
企業の皆様にとって、ゼロトラストは現代のビジネス環境において不可欠なセキュリティ戦略です。全てのデータを守るべき資産と捉え、「何も信じない」という前提で、常に検証し続けるアプローチを取り入れることで、変化の激しい脅威から企業を守り、持続的な成長を支えることができるはずです。