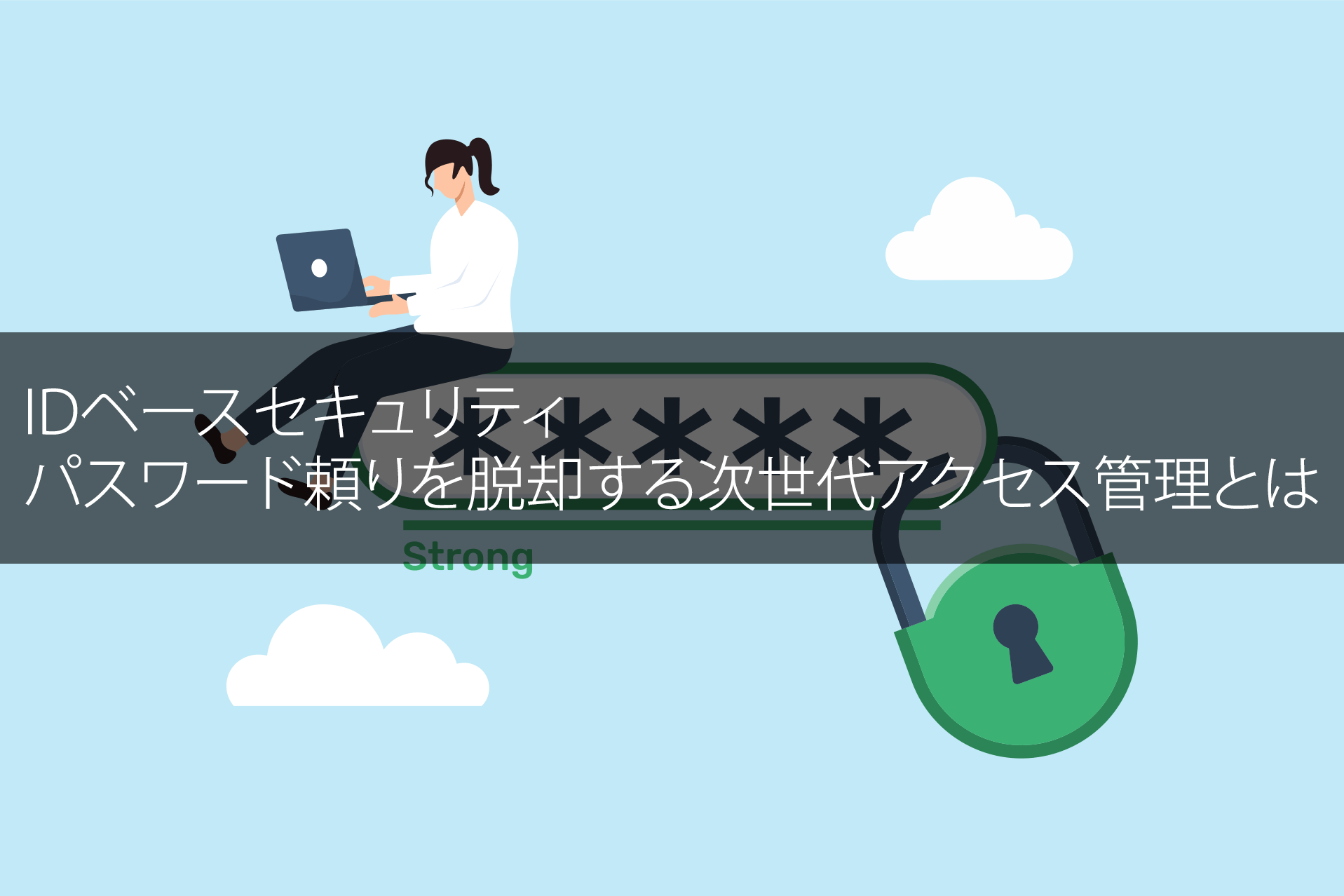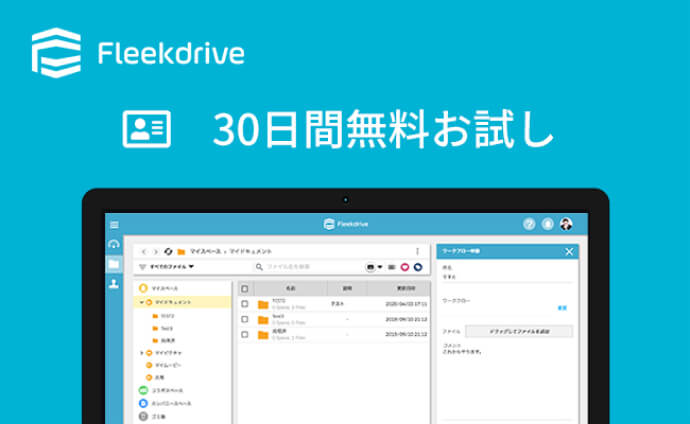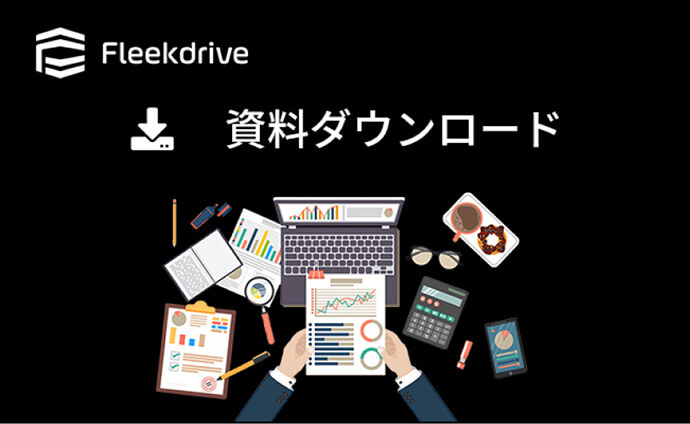「SaaSが増えID管理が限界…」「退職者のアカウントが不安…」「テレワークのセキュリティは大丈夫か?」
組織においてこうしたアクセス管理の課題が尽きません。従来の境界型防御が通用しない今、企業のセキュリティを守る鍵は「ID」を中心としたアクセス管理にあります。適切なアクセス管理は、不正侵入を防ぐ強固なセキュリティの要です。本記事では、この新たな脅威に対応するための次世代アクセス管理を解説します。
Contents
なぜ今、アクセス管理がセキュリティの核なのか?
かつては、堅牢な城壁(ファイアウォール)で社内ネットワークを囲い、その内側を守るのがセキュリティの基本でした。しかし、ビジネス環境が劇的に変化したことで、この城壁は意味をなさなくなりつつあります。
背景1:クラウド化による「IDの氾濫」と管理の限界
今や、業務に複数のSaaS(Software as a Service)を利用するのは当たり前です。その結果、従業員一人ひとりが多数のIDとパスワードを保有し、情報システム部門はそのすべてを把握・管理することが困難になりました。部署が独自に契約してしまうシャドーITも横行し、誰が・どのデータに・どこからアクセスできるのか、その全体像はブラックボックス化しがちです。このIDの氾濫こそが、セキュリティホールを生む温床となっています。
背景2:働き方の多様化による「境界」の消失
テレワークやモバイルワークの普及により、従業員は自宅、カフェ、出張先など、様々な場所・デバイスから企業のデータにアクセスします。もはや「社内IPアドレスからのアクセスだから安全」という前提は成り立ちません。守るべきデータとアクセスする利用者が社内外に分散したことで、アクセス管理の拠り所となるべき境界そのものが消失してしまったのです。
背景3:攻撃手法の主流となった「認証情報の窃取」
サイバー攻撃者は、この変化を巧みに突いてきます。彼らの主な攻撃手法は、システムの脆弱性を突くよりも、フィッシング詐欺やダークウェブで不正に入手したID・パスワードリストを使って正規ユーザーになりすますことです。一度認証を突破されてしまえば、攻撃者は内部で自由に活動し、重要な情報を窃取したり、ランサムウェアを展開したりすることが可能になります。つまり、入り口である認証の強化が、これまで以上に死活問題となっているのです。
これらの背景から、現代のセキュリティはすべてのアクセスを疑い、その正当性をIDに基づいて都度検証するというアプローチ、すなわちゼロトラストの考え方に基づいたアクセス管理が不可欠となっています。
セキュリティを強化するアクセス管理の具体的な対策
では、IDを中心とした次世代のアクセス管理は、どのように実現すればよいのでしょうか。企業が取り組むべき3つの重要なアプローチをご紹介します。
対策1:ID管理の一元化とシングルサインオン(SSO)
散在するIDを集約し、認証の基盤を一つにまとめることが第一歩です。これを実現するのがIDaaS(Identity as a Service)やIAM(Identity and Access Management)と呼ばれるソリューションです。
業務への活かし方
- シングルサインオン(SSO)の実現: 従業員は一度の認証で、許可された複数のクラウドサービスへパスワード入力なしでアクセスできるようになります。これにより、ユーザーの利便性が劇的に向上すると同時に、パスワードの使い回しといったリスクを低減できます。情シス部門にとっても、問い合わせ対応の工数が削減されるというメリットがあります。
- シャドーITの可視化: SSOの導入を機に、社内で利用されているSaaSを洗い出し、正式な管理下に置くことで、セキュリティガバナンスを強化できます。
対策2:多要素認証(MFA)の徹底と脱パスワード
IDとパスワードの組み合わせだけでは、もはや安全とは言えません。そこで不可欠となるのが多要素認証(MFA:Multi-Factor Authentication)です。
多要素認証とは?
「知識情報(パスワードなど)」「所持情報(スマートフォンアプリ、物理キーなど)」「生体情報(指紋、顔認証など)」のうち、2つ以上の要素を組み合わせて本人確認を行う仕組みです。
業務への活かし方
- 万が一パスワードが漏洩しても、攻撃者は第二の認証要素(本人のスマートフォンなど)を持っていないため、不正アクセスを水際で防ぐことができます。
- 特に、管理者権限を持つアカウントや、機密情報にアクセスするシステムへのMFA適用は、セキュリティ対策の基本中の基本です。
対策3:アカウントライフサイクル管理の自動化
「退職者のアカウント削除漏れ」は、内部不正や情報漏洩に繋がる重大なリスクです。このヒューマンエラーを防ぐのが、プロビジョニングとデプロビジョニングにおける自動化の仕組みです。
業務への活かし方
- 人事システムとID管理システムを連携させます。これにより、人事データベースに入社情報が登録されると、業務に必要なアカウント群が自動で作成され、適切な権限が付与されます。
- 逆に、退職や異動の情報が登録されると、関連するすべてのアカウントが速やかに停止(無効化)されます。これにより、手作業による対応漏れを根本的になくし、アクセス管理の正確性と即時性を担保します。
アクセス管理導入で失敗しないセキュリティのポイント
これらの対策をスムーズに導入し、形骸化させないためには、いくつかの重要なポイントがあります。
ポイント1:現状把握から始める「ID棚卸し」
新しいシステムを導入する前に、まずは自社に「誰の」「どのアカウントが」「どのような権限で」存在しているのかを徹底的に洗い出すIDの棚卸しが不可欠です。使われていない休眠アカウントや、退職者の残存アカウント、過剰な権限が付与されたアカウントなどを可視化することで、自社のリスクを正確に把握し、対策の優先順位を決めることができます。この地道な作業こそが、プロジェクト成功の土台となります。
ポイント2:利用部門を巻き込む利便性という視点
セキュリティ強化は、時にユーザーの業務に制約を加えることになります。一方的なルール徹底は、現場の反発を招き、抜け道(シャドーIT)を探す動機にもなりかねません。そこで重要なのが、セキュリティと利便性の両立です。
利用部門の代表者をプロジェクトに巻き込み、意見を吸い上げながら進めることで、全社的な協力を得やすくします。
ポイント3:責任の所在を明確にする「役割分担」
アクセス管理は、情報システム部門だけの仕事ではありません。
- 人事部門: 正確な従業員情報の提供源
- 各事業部門長: 配下メンバーの業務内容を把握し、必要なアクセス権限を判断・承認する責任者
- 情報システム部門: 全体的なポリシーを策定し、システムを構築・運用する役割
これらの役割と責任分担を明確に定義し、全社的なルールとして合意形成することが、継続的で実効性のあるアクセス管理体制の構築に繋がります。
今後のセキュリティ動向とアクセス管理の未来
アクセス管理の技術は、今も進化を続けています。今後の重要なトレンドを2つご紹介します。
- パスワードレス認証の本格化
パスワードという概念そのものをなくし、より安全で便利な認証方式へ移行する動きが加速しています。FIDO2などの国際標準規格に対応した生体認証(顔や指紋)や、PCに挿すだけの物理的なセキュリティキーが、パスワードに取って代わる未来はすぐそこまで来ています。 - AIによる動的なリスク評価と自動対応(UEBA)
AIが一人ひとりの普段の働き方(利用時間、アクセス場所、使用デバイス、操作内容など)を学習します。そして、そのパターンから逸脱した異常な振る舞い(例:深夜に機密ファイルへ大量アクセス)を検知すると、リアルタイムでリスクを評価。リスクレベルに応じて、自動的にアクセスをブロックしたり、追加の認証を要求したりといった対応が可能になります。これはUEBA(User and Entity Behavior Analytics)と呼ばれ、内部不正やアカウント乗っ取りの早期発見に絶大な効果を発揮します。
まとめ:セキュリティとDXを支えるアクセス管理の重要性
サイバー攻撃が巧妙化し、ビジネス環境が複雑化する現代において、アクセス管理はもはや単なる「守り」のセキュリティ対策ではありません。それは、従業員が安全かつ効率的に業務を遂行し、企業が安心してDXを推進するための攻めのIT基盤です。
皆様はこの攻めの基盤を設計・構築し、企業の競争力を根幹から支える戦略的な役割を担っています。ID管理の最適化は、セキュリティ強化、業務効率化、そして従業員満足度の向上という、一石三鳥の効果をもたらすポテンシャルを秘めています。
まずは自社のID管理の現状を見直し、どこにリスクと改善の余地があるのかを特定することから始めてみてはいかがでしょうか。