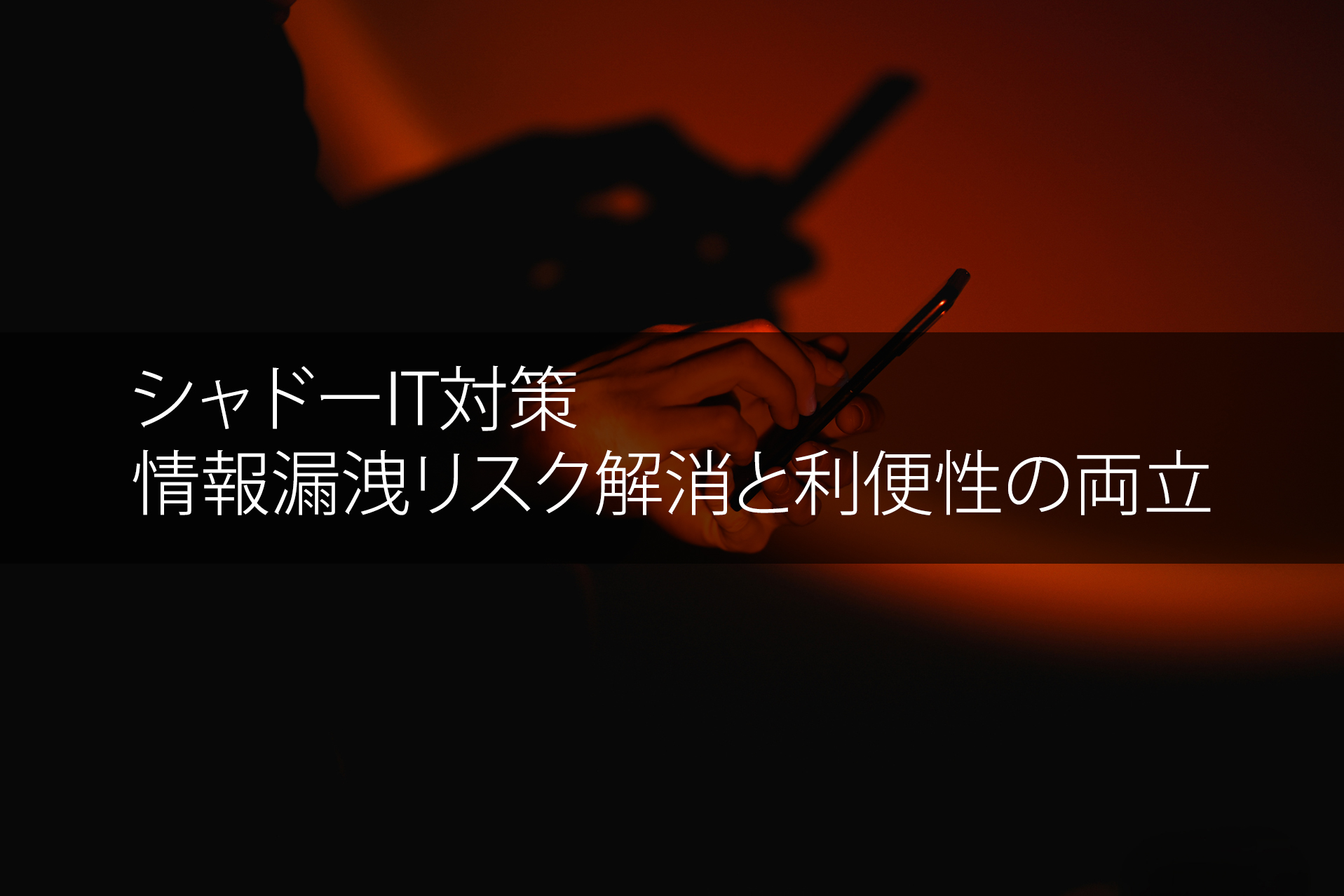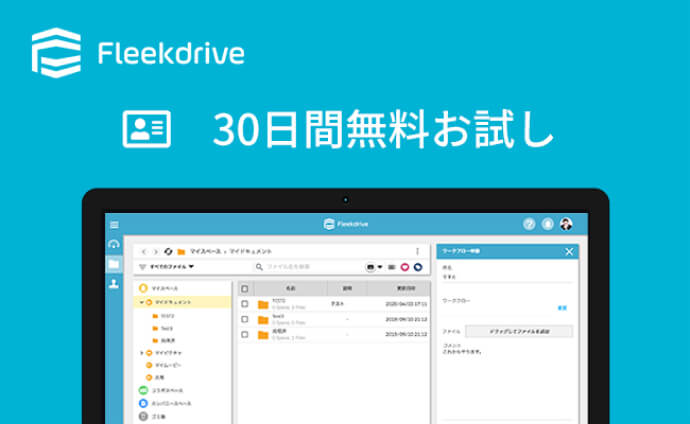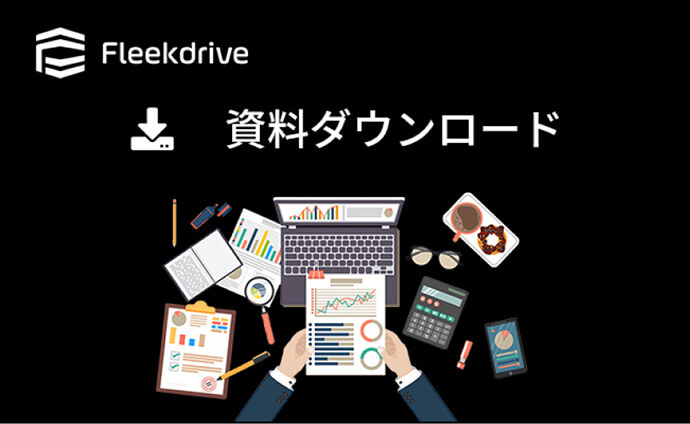現場部門の「使いやすさ」を追求した結果、承認されていないクラウドサービス(シャドーIT)が蔓延し、情報漏洩対策上の最大の盲点となっていませんか。特にファイル共有のセキュリティ統制が取れていない状態は、法人向けの高セキュリティ体制を根底から崩します。本記事は、シャドーITが生まれる真の原因を明らかにし、現場の利便性を損なわずにリスクを解消する対策手順を解説。あわせて、シャドーITの実態把握から代替手段への移行までを一貫させる実務対策の勘所も提示します。
Contents
シャドーIT対策が不可欠となる3つの深刻なリスク
シャドーITは、一時的な業務効率化をもたらす反面、法人のセキュリティ体制に深刻な構造的リスクを組み込みます。
情報漏洩とデータガバナンスの崩壊
シャドーITで利用されるファイル共有サービスの多くは、法人向けの高セキュリティ要件(監査ログ、IPアドレス制限、詳細なアクセス権限管理など)を満たしていません。機密ファイルがシャドーIT上で共有された場合、情報システム部門のデータガバナンスの目が行き届かなくなり、誰が、いつ、どこから、どんなファイルを閲覧・共有したかの記録が残りません。これにより、情報漏洩が発生した場合に流出経路の特定ができず、初動対策が完全に遅れることになります。
コンプライアンス違反と法的責任の発生
承認されていないファイル管理サービスを業務に利用することは、企業が定めるセキュリティポリシーやコンプライアンス規則への違反に直結します。特に、個人情報や機密性の高いデータを扱う場合、そのサービスのデータ保存場所(国内外)やセキュリティ基準が、日本の法令や業界規制(例:GDPRなど)を満たしていない可能性があり、万が一の事故の際に法人としての法的責任を問われるリスクがあります。
アカウント管理の属人化と内部不正リスク
シャドーITのアカウントは、現場の担当者が個人メールアドレスで作成・管理しているケースが多く、退職者発生時にアカウント削除やデータ保全の手順が確立されていません。このアカウント管理の属人化は、離職者による機密データの不正持ち出しや、アカウントの悪用といった内部不正リスクを増大させます。
シャドーIT対策の前提:「統制」と「利便性」の不均衡
シャドーITは、従業員が意図的にセキュリティを軽視しているわけではなく、企業が提供する既存システムが「使えない」ために発生しています。
現場の「利便性」を無視したファイル管理システムの弊害
シャドーITの最大の発生原因は、既存のファイル管理システムが現場のニーズに応えられていないことです。具体的には、「大容量ファイルの共有が遅い」「社外の協力会社とのファイル共有が複雑すぎる」「スマホやタブレットからのアクセスが許可されていない」といった利便性の欠如が、従業員をより使いやすいシャドーITへ向かわせます。シャドーIT対策は、セキュリティを強化しつつも、現場の利便性を向上させる法人向けソリューションの導入によってのみ実現可能です。
承認されていないサービスの可視化
シャドーIT対策の第一歩は、シャドーITの利用実態を把握することです。情報システム部門は、ネットワークログやCASB(Cloud Access Security Broker)ツールなどを利用して、ファイル共有に関する未承認のクラウドサービスへのアクセスを可視化する手順を実行する必要があります。ただし、可視化と同時に、なぜそのシャドーITが使われているのかという現場のニーズをヒアリングすることが、後の解消(統制化)を成功させる鍵となります。
シャドーIT対策の手順:法人向け高セキュリティソリューションの選定基準
シャドーITを「禁止」するのではなく、「統制された代替手段」に置き換えることが、永続的な情報漏洩対策となります。
統制と利便性を両立する高セキュリティ機能
法人向けオンラインストレージは、現場が求める「使いやすさ」と情シスが求める「高セキュリティ」を両立できる機能が選定基準となります。
- アクセス権限管理の柔軟性:外部共有時のダウンロード禁止/有効期限/透かし印字など。
- 認証・ログ:MFA、IP制限、全操作の監査ログ、証跡のエクスポート。
- 共有リンクの制御:パスワード・ドメイン制限・リンク失効の自動化。
シャドーIT対策は利便性を提供する「攻めのセキュリティ」
シャドーIT対策は、情報漏洩リスクを解消し、データガバナンスを確立するための「守りのセキュリティ」であると同時に、現場の利便性を向上させる「攻めのセキュリティ」でもあります。禁止ではなく置き換えへ。高セキュリティなアクセス権限管理とワークフロー自動化を備えた法人向けストレージへ誘導し、シャドーITのニーズを満たす正規の仕組みで運用しましょう。