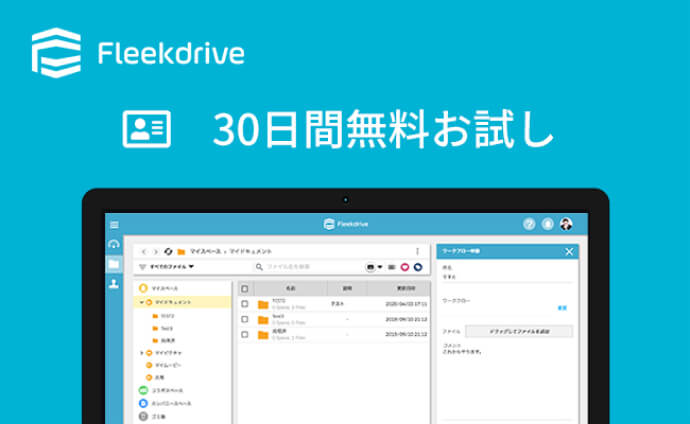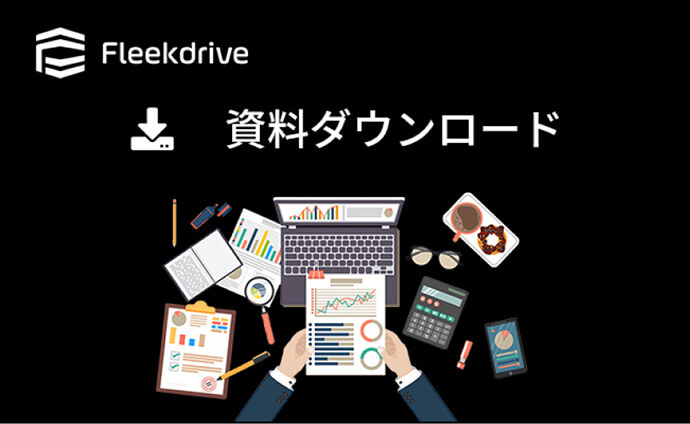「備えあれば憂いなし」と言われますが、災害などの緊急時を想定してBCP(事業継続計画)対策の意識が高まっています。情報システムに関していえば、データアクセスを確保することが大切です。このときクラウドストレージが役立ちます。本記事では、BCP担当者が緊急時に求められることを挙げるとともに、クラウドストレージ活用のヒントを解説します。
Contents
緊急事態の発生時にBCP担当者が実行する5つのポイント
東日本大震災をきっかけにして、防災対策が重視されるようになりました。多くの企業では、BCPのための組織づくりや具体的なルールの制定に取り組んでいます。緊急時に直面したときにBCP担当者は何をすべきか、災害時の流れにしたがって5つのポイントを挙げます。
従業員の安否確認と安全の確保
何よりも優先すべきことは、従業員全体の安否確認と安全の確保です。緊急時には、通信が使えない場合があります。したがって電話、メール、チャット・SNS、アプリなど複数の手段で確認できるようにしておきましょう。スマートフォンアプリの安否確認サービスの導入も進んでいます。緊急連絡網を定めておき、安全が確認できない従業員の適切な対応を指示します。けがなどがあった場合には具体的な対応を示し、避難が必要であれば誘導します。
施設や建物の被災状況と安全の確認
オフィスが被災した場合は、建物の損壊のほか、電気・水道・ガスなどインフラの状況を確認します。財務関係などの基幹システムの稼働についてもチェックします。社内にサーバやストレージなどを置いている場合は、設備の被害状況を調べることが必要です。インターネットや社内のLANのほか、従業員の使っているパソコンなどの端末が利用できるかどうか把握します。バックアップやデータを記録メディアで保管している場合、顧客情報のような機密情報が安全な状態にあるか注意が必要です。
すみやかなBCPの実行
従業員やオフィスの被災状況の確認からがBCPの一部といえますが、状況を把握した上で、あらかじめ計画していた事業継続のプランを実行に移します。業務のうち再開できるものは再開し、一部の業務は一時的に中断させ、業務形態をリモートワークに切り替えて勤務時間帯のシフト変更を指示します。SaaSやクラウドストレージを使っている場合は、自宅からのインターネット接続が可能であれば、スムーズに在宅勤務に移行することが可能です。
被害状況の把握、優先あるいは代替すべきことの決定
被害状況は時間にしたがって変わります。地震の場合、火災や停電などの二次災害が発生する場合も考えられます。災害発生時に確認できなかった状況のほか、従業員の家族についても把握が必要です。リアルタイムで現状を確認し、被害状況を更新します。このときメールを使うと迅速な情報共有ができますが、やりとりが煩雑になりがちです。クラウドストレージ上のファイルを使って情報を集約すると、オンラインの特別なシステムを使わずに情報共有が可能になります。
ステークホルダー全体への報告
大きな災害時には、社内の対応だけでせいいっぱいかもしれません。しかし、社外への対応も必要です。不安な状況を放置しておくと、さまざまな憶測が生まれやすいからです。企業のレピュテーション・マネジメント(風評被害の抑制)の観点を踏まえて、会社のホームページなどを使って現状の報告と対応の方針、今後の見込みなどを報告します。なるべく迅速に情報発信することが望ましいですが、段階的な報告でも構いません。逐次的に現状を伝えることにより、取引先や従業員の家族などから幅広い信頼を得られることでしょう。
緊急時のデータアクセスで注意すべきこと
緊急時のBCP対応について一般的なポイントをまとめました。情報システム系に焦点を当てると、業務を継続させるためには、データアクセスが重要になります。在宅など社外からデータにアクセスできる通信やネットワークを確保し、損害を受けたデータをバックアップから復旧させます。その2つについて注意すべきことを整理します。
通信環境、ネットワークの確保
オフィスワークからリモートワークに移行する際には、まず通信環境を確保する必要があります。自宅のPCやインターネット接続が使えなくても、スマートフォンから通信できる可能性が残されています。スマートフォンは常に携帯していることから場所を判別しやすく、報告書など簡単な文書であれば作成できます。ただし、震災などの状況では通信がつながりにくく、病気やけがなど緊急連絡を優先する心がけも大切です。
バックアップからの復旧
オフィスの建物が損壊するなど大きな被害に際しては、会社のPCやサーバなどの設備が使えなくなり、業務に必要なデータそのものが失われることがあります。このような状況を想定して、日頃からクラウドストレージを活用しておくと緊急時の備えになります。クラウドストレージ上のデータは、あらゆる場所からアクセスが可能です。バックアップを迅速に復旧できることから、日常業務を継続させるために役立ちます。
緊急時のクラウドストレージ活用
ここからは緊急時にクラウドストレージを活用する方法として、社内の被災状況を把握する情報共有の使い方と、リモートワークによる業務の継続についてまとめます。
被害状況の報告を集約し、リアルタイムで情報を共有
災害時の情報共有を考えると、メールは個別のやりとりになり、同報で送信したときに確認が煩雑になります。チャットは、スレッドが追いにくい欠点があります。災害用掲示板など特別なサービスの利用も考えられますが、クラウドストレージの活用も便利な面があります。クラウドストレージに報告用のファイルを置き、従業員が各々アクセスして情報を記入し、被災状況を集約します。写真をアップロードすれば、テキストよりも明確に把握できます。情報更新時には自動的にリマインドメールを送信させることも可能です。
リモートワークによる業務の再開と継続
緊急時に業務を継続するときは、リモートワークへの移行が必要です。このとき、クラウドストレージに保存したファイルやデータを使えば、ふだんと同じように業務を続けられます。Fleekdriveはスマートフォンなどモバイル活用の機能が充実し、高度なセキュリティで安全に利用できる環境を備えています。また、共同編集時に誤ってファイルの上書きをしないように知らせる機能もあります。変更したファイルのバージョン管理も備えているため、過去のファイルに遡ることも可能です。
災害時のリスクを低減させるには、日頃からの備えが大切
防災は日頃からの備えが大切であり、災害時に特別な対応をしなくても事業を継続できる仕組みづくりが重要なポイントです。安否確認サービスなどの利用とともに、災害発生時以降の事業の継続を考える必要があります。日頃からクラウドストレージを活用していれば、在宅の環境でも違和感なく使い続けられます。災害時の状況把握からリモートワークへの移行まで、シームレスなデータアクセス環境を確保できます。
まとめ
災害を想定したBCP対策が重視されるようになりました。しかし、緊急時だけを考えた対策では、実際に災害に直面したときにストレスが大きく、想定していなかった問題も発生します。日頃からクラウドストレージを使って情報を共有していれば、安否確認などの現状の把握からリモートワークまで、災害時にも通常と同じように業務を続けることができます。災害対策にクラウドストレージの活用をお考えなら、ぜひFleekdriveをご検討ください。