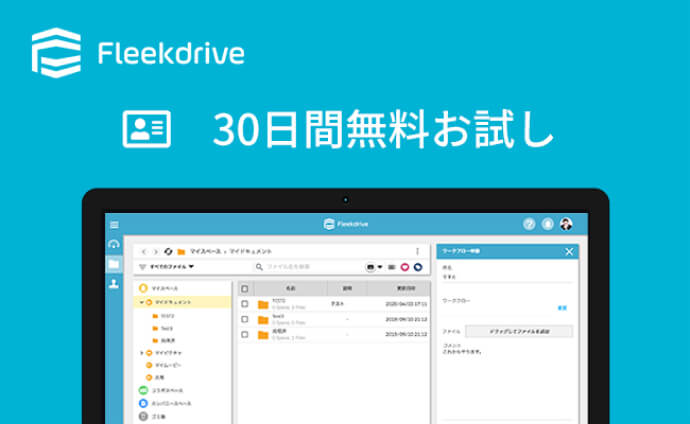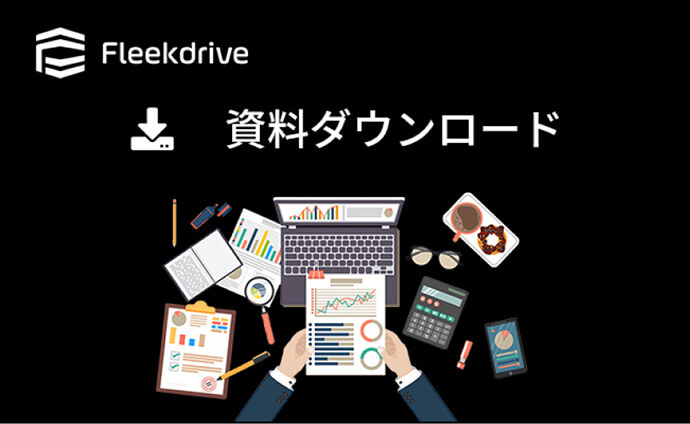急速な技術進化に伴い、サイバー犯罪の手口はますます巧妙化し、ウェブセキュリティに関する脅威は深刻さを増しています。企業や組織は、常に最新の脅威に対応し、自社の情報資産を守るための脅威対策を講じることが不可欠です。本記事では、現代のウェブセキュリティにおける3つの主要な脅威を深く掘り下げ、それぞれの概要と効果的な脅威対策について解説します。
Contents
深刻化するウェブセキュリティの脅威
近年のサイバー攻撃は、その規模と頻度において拡大の一途をたどっています。総務省やNICTの調査によると、サイバー攻撃関連のパケット数は年々増加しており、2023年には6,000億パケットを突破しました。
また、IPA(情報処理推進機構)が発表した「情報セキュリティ10大脅威 2025(組織編)」では、「ランサムウェアによる被害」が10年連続で上位にランクインし1位に、次いで「サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃」が2位となっています。これらのデータからも、企業が直面する脅威の深刻さがうかがえます。
(出典: 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)『情報セキュリティ10大脅威 2025』)
【脅威1】ランサムウェア攻撃への脅威対策
ランサムウェア攻撃は、企業のデータを不正に暗号化したり、データを盗み出したりして、その復旧や非公開と引き換えに身代金を要求するサイバー攻撃です。近年では、データを暗号化せずに「盗んだ情報を公開する」と脅す「ノーウェアランサム」という手口も登場しています。
ランサムウェア攻撃の現状
この攻撃は、大企業だけでなく中小企業にも深刻な被害をもたらしています。警視庁の報告によると、令和5年に発生した被害197件のうち、中小企業が102件(52%)と半数以上を占めています。
また、被害額も甚大で、2024年度の調査では1社あたりの平均被害額が2億2,000万円に上り、中には10億円以上の損失を計上した企業も報告されています。
主な防御策と対策
- ゼロトラストセキュリティモデルの構築
従来の「社内は安全、社外は危険」という境界型セキュリティモデルではなく、「すべてのアクセスを信頼しない」ことを前提とするゼロトラストモデルを構築します。これにより、社内外を問わずすべての通信やアクセスを検証し、脅威の侵入と拡散を防ぎます。 - 「最小権限の原則(PoLP)」の徹底
ユーザーやシステムには、業務遂行に必要な最低限のアクセス権限のみを付与します。これにより、万が一IDが乗っ取られた場合でも、被害の範囲を最小限に抑えることができます。 - 定期的なバックアップと分離管理
重要なデータは定期的にバックアップを取得し、ネットワークから分離されたオフライン環境で保管します。また、バックアップデータが正常に復元できるかを定期的にテストすることも不可欠です。
【脅威2】サプライチェーン攻撃とウェブセキュリティ
サプライチェーン攻撃は、ターゲット企業に直接侵入するのではなく、セキュリティ対策が手薄になりがちな取引先や子会社、業務委託先などを踏み台にして、間接的にターゲットのネットワークへ侵入する攻撃手法です。
サプライチェーン攻撃の背景
なぜサプライチェーンが狙われるのでしょうか。
- 大手企業のセキュリティ強化: ターゲットとなる大手企業のセキュリティが強化され、直接侵入が困難になったため。
- 取引先の脆弱性: 中小企業であるサプライヤーは、大手企業と同レベルのセキュリティ対策を講じることが難しい場合が多い。
- 信頼関係の悪用: 攻撃者は、企業間の信頼関係を悪用し、正規の取引を装って侵入を試みる。
これにより、攻撃者はサプライチェーン全体に影響を及ぼし、多額の身代金を要求することが可能になります。
サプライチェーン攻撃への脅威対策
- セキュリティ評価の実施
取引先と契約する際に、自社が求めるセキュリティ要件を提示し、それが満たされているかを定期的にアセスメント(評価)します。対策が不十分な場合は、取引の見直しや改善監査を行います。 - 導入ソフトウェアの信頼性を検証
業務で利用するソフトウェアは、正規の配布元から入手することを徹底します。特にサードパーティ製のツールやライブラリを利用する際は、改ざんされていないかを確認し、信頼性を検証します。 - 脆弱性の把握 (SBOMの活用)
製品に含まれるOSS(オープンソースソフトウェア)の構成要素や依存関係を一覧化したリストであるSBOM(Software Bill of Materials)を活用し、ソフトウェアに潜む脆弱性を可視化・把握します。
【脅威3】データ漏洩と内部不正
リモートワークの普及に伴い、従業員の行動が新たなセキュリティリスクを生む要因となっています。内部からの情報漏洩や、従業員の過失を突いた不正アクセスも依然として重大な脅威です。
データ漏洩と内部不正の背景(リモートワーク特有の課題)
- BYOD(個人デバイス)の使用: セキュリティ対策が不十分な個人PCやスマートフォンを業務に利用することで、マルウェア感染のリスクが高まります。
- 公共Wi-Fiの利用: カフェなどの公共Wi-Fiは通信が暗号化されていない場合が多く、通信内容を盗聴される危険性があります。
- VPNの限界: 境界型セキュリティの要であるVPNも、一度突破されると内部ネットワークへの侵入を許してしまいます。また、内部の人間による不正行為はVPNでは防げません。
内部不正への脅威対策
- DLP(Data Loss Prevention)ツールの導入
DLPツールは、機密データの移動や送信を監視・制御し、情報漏洩を未然に防ぎます。USBデバイスの使用制限、印刷やコピーの制御、特定のWebサイトへのアクセス禁止などの対策が可能です。 - アクセス管理の徹底
多要素認証(MFA)を導入し、IDとパスワードだけの認証に頼らない仕組みを構築します。また、退職した社員のアカウントは速やかに削除し、パスワードの使い回しを禁止するなど、厳格なアカウント管理が求められます。 - エンドポイントセキュリティと教育
PCやスマートフォンといったエンドポイント(端末)に対するセキュリティ対策を強化します。さらに、フィッシング詐欺や標的型攻撃メールを見抜くための訓練など、従業員への継続的なセキュリティ教育が極めて重要です。
まとめ:ウェブセキュリティ強化のための脅威対策アクション
複雑化するサイバー攻撃に対抗するためには、企業は包括的なセキュリティ戦略を策定し、継続的に対策を講じる必要があります。特に重要なアクションは以下の3つです。
- セキュリティツールの活用
ゼロトラストの考え方を基盤にツールを見直し、最新の脅威に対応できる製品を導入します。AIを活用したリアルタイム検知や、エンドポイントセキュリティなどを統合したXDR(Extended Detection and Response)ソリューションも有効です。 - 定期的な脆弱性診断
社内システムやクラウド環境、IoTデバイスなどに対し、定期的に脆弱性診断を実施します。ペネトレーションテスト(侵入テスト)などを通じて、自社のシステムの弱点を客観的に把握し、対策を講じます。 - 社内外のセキュリティ教育
サイバー攻撃における最大の脆弱性は「人」です。従業員の不正やヒューマンエラーを防ぐため、フィッシングメールの模擬訓練など、実践的な教育を徹底します。この教育は、社内だけでなく、サプライヤーも含めた関係者全体で実施することが望ましいです。
この記事で解説した脅威対策を参考に、自社のセキュリティ体制を見直し、安全な事業活動の基盤を築きましょう。
本記事で解説した「ウェブセキュリティの脅威と対策」のポイントをまとめた資料を、以下より無料でダウンロードいただけます。ぜひ貴社のウェブセキュリティ強化にお役立てください。