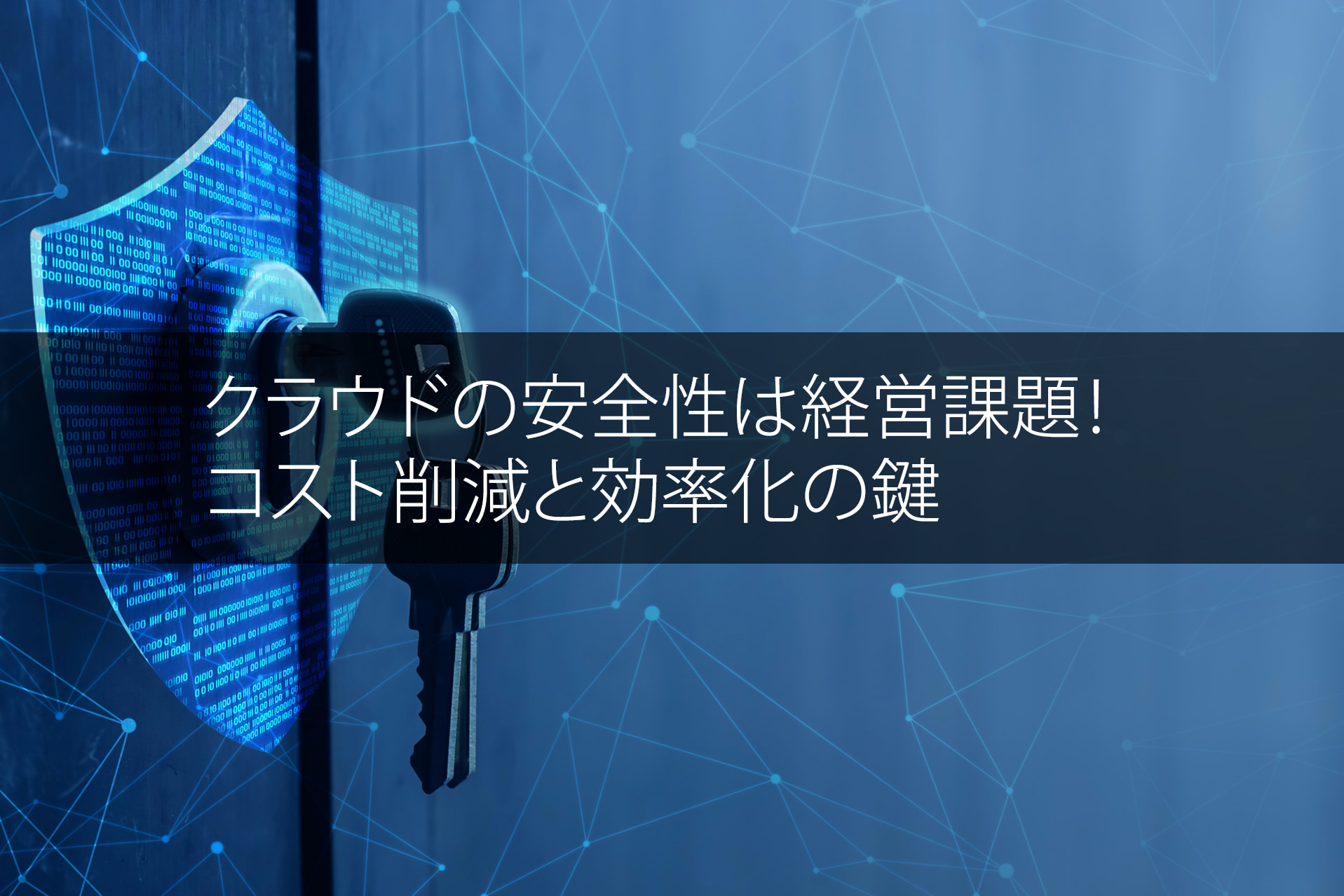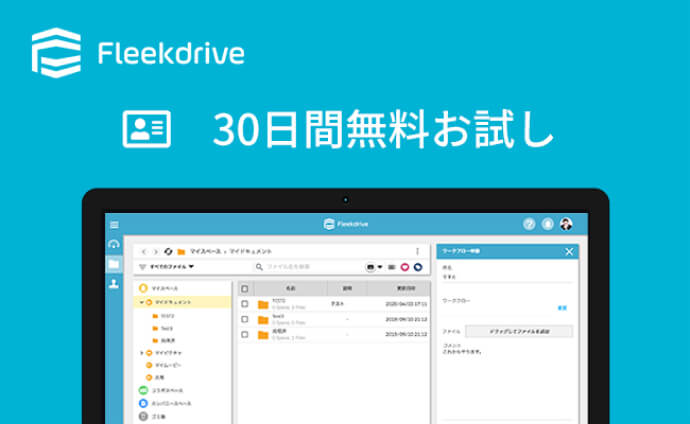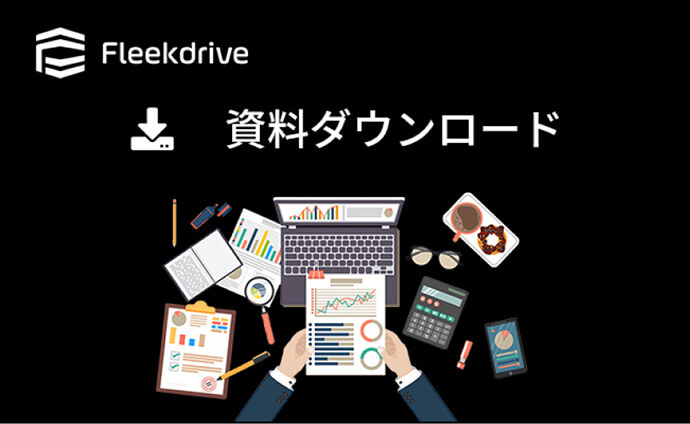「業務を効率化したいが、情報漏洩を考えると不安だ」多くの企業担当者が抱えるこの課題。
DX推進が不可欠な今、クラウド導入を躊躇させる最大の要因が、この安全性に対する懸念ではないでしょうか。しかし、現在の法人向けクラウドサービスは、自社でサーバを運用する以上に高いレベルの安全性を確保できます。本記事ではクラウドがもたらすコスト削減や生産性向上というメリットを、安全性という視点から解説します。
Contents
クラウドの安全性と比較する、オンプレミスの3つの課題
クラウド導入を検討する前に、まずは現状のデータ管理方法、特に社内にサーバを設置するオンプレミス環境が抱える課題を再確認しましょう。多くの企業が当たり前としてきたこの環境には、クラウドと比較して見過ごせないリスクとコストが潜んでいます。
課題1:避けられない物理的リスク(災害・盗難・故障)
オフィスやデータセンターの片隅に設置されたサーバは、常に物理的なリスクに晒されています。
- 自然災害: 地震によるサーバラックの転倒、台風や豪雨による浸水、火災による焼損など、日本は自然災害のリスクと常に隣り合わせです。万が一サーバが物理的に破損した場合、そこに保存されていた業務データが失われ、事業継続が困難になる深刻なリスクがあります。
- 盗難・不正侵入: 悪意のある第三者や内部関係者がサーバ室に侵入し、サーバ本体やハードディスクを盗み出すリスクもゼロではありません。
- ハードウェア故障: サーバは精密機械です。経年劣化によるハードディスクのクラッシュやマザーボードの故障は突然発生します。定期的なバックアップがなければ、重要なデータを復旧できなくなる恐れがあります。
自社でこれらのリスクに24時間365日備えるには、免震構造の建物、自家発電装置、厳重な入退室管理システムなど、莫大な投資が必要です。
課題2:見えないコストが増え続ける運用・管理の負担
サーバ運用には、機器の購入費用以外にも、継続的に発生する見えないコストが存在します。
- 人的コスト: サーバの監視、OSやソフトウェアのアップデート、トラブル対応などを行う情報システム部門の人件費。専門知識を持つ人材の確保や育成も大きな負担です。
- 設備コスト: サーバを安定稼働させるための電気代、サーバ室を一定の温度に保つための空調費は、24時間発生し続けます。
- 更新・保守コスト: サーバ機器は通常5年程度で寿命を迎えるため、定期的な買い替えが必要です。また、メーカーとの保守契約費用や、ソフトウェアのライセンス更新費用も毎年発生します。
これらのコストは、事業規模の拡大に伴って増大し、企業の利益を圧迫する要因となり得ます。
課題3:テレワーク時代の情報共有の壁とセキュリティリスク
働き方が多様化し、テレワークが普及したことで、従来のデータ管理方法の限界が浮き彫りになりました。
- アクセスの問題: 社外から社内サーバに安全にアクセスするためには、VPNの構築が必要ですが、設定が複雑で、通信速度が遅くなることも少なくありません。「会社に行かないとあのファイルが見られない」といった非効率が発生します。
- 危険なデータの持ち出し: アクセスの不便さから、従業員がUSBメモリや個人のPCに業務データをコピーして持ち帰るケースが増加します。これは、USBメモリの紛失や盗難による重大な情報漏洩事故に直結する、非常に危険な行為です。
- PPAP問題: パスワード付きZIPファイルをメールで送る「PPAP」は、セキュリティ対策として無意味であるだけでなく、ウイルスチェックをすり抜ける危険性や、受信者の手間を増やす問題が指摘されています。
クラウドの物理的な安全性:災害・盗難からのデータ保護
オンプレミスが抱える物理的なリスクは、質の高いクラウドサービスを導入することで解決できます。クラウドが提供する物理的な安全性について解説します。
堅牢なデータセンターという要塞
クラウド事業者が運営するデータセンターは、まさにデータの要塞です。
- 災害対策: 震度7クラスの地震にも耐える免震・耐震構造、水害リスクの低い立地選定、複数系統の受電設備や自家発電装置、ガスによる消火設備などを完備しています。これにより、あらゆる自然災害からデータを守ります。
- 侵入対策: 24時間365日の有人監視、監視カメラ、生体認証などを含む多段階の入退室管理システムにより、権限のない人物の侵入を物理的にブロックします。
自社のオフィスビルの一室にサーバを置くことと比較すれば、その安全性のレベルの違いは明らかです。
データの冗長化による消失リスクの低減
多くのクラウドサービスでは、データは複数のサーバや複数の拠点にまたがって、自動的に複製・保存(冗長化)されています。仮に一つのハードディスクやサーバが故障しても、冗長化された別のサーバが処理を引き継ぐためサービスが継続され、データが失われるリスクを最小限に抑えられます。災害などで一つのデータセンターが機能しなくなった場合でも、遠隔地の別のデータセンターで事業を継続できる仕組み(ディザスタリカバリ)を備えているサービスも多く、事業継続性(BCP)を飛躍的に高めます。
クラウドの技術的な安全性:サイバー攻撃と内部不正への備え
物理的な防御壁に加え、クラウドサービスは日々巧妙化するサイバー攻撃や、予期せぬ内部からの情報漏えいを防ぐ技術的な側面や仕組みなど高い安全性を確保しています。
専門家による24時間365日の監視体制
クラウド事業者は、セキュリティの専門家集団を抱えています。彼らが24時間365日、システムの稼働状況や不正なアクセスの兆候を監視し、最新のサイバー攻撃からデータを守っています。
- 高度な技術的対策: 不正アクセス検知・防御システム(IDS/IPS)やWAF(Web Application Firewall)などを導入し、外部からの攻撃を多層的に防御します。
- 迅速な脆弱性対応: システムの脆弱性が発見された場合でも、専門チームが迅速にセキュリティパッチを適用。自社で情報収集から対応まで行うのに比べ、圧倒的にスピーディかつ確実です。
- データの暗号化: 通信経路(データ送受信時)と保存領域(データ保管時)の両方でデータが暗号化されるため、万が一データが盗み見られたとしても、内容を解読することは極めて困難です。
柔軟なアクセス制御と証跡管理
情報漏えいは、外部からの攻撃だけでなく、内部の従業員による誤操作や不正行為が原因となるケースも少なくありません。クラウドサービスは、こうした内部リスクを管理・統制するための機能も充実しています。
- 詳細なアクセス権限設定: ユーザーごと、あるいは部署やプロジェクトチームごとに「閲覧のみ」「編集可能」「ダウンロード禁止」といった細かいアクセス権限を設定できます。
- 操作ログ(監査ログ)の取得: 「いつ」「誰が」「どのファイルに」「何をしたか」といった操作履歴がすべて自動で記録されます。これにより、不正操作を心理的に抑止し、万一の際の原因究明を迅速化します。
これらの機能により、PPAPやUSBメモリに頼ることなく、テレワーク環境でも安全かつ効率的な情報共有が実現します。
クラウドの高い安全性がもたらすコスト削減
クラウド導入は、単にセキュリティを強化するだけにとどまりません。その高い安全性を基盤として、直接的な経営上のメリットを生み出します。
TCO(総所有コスト)の最適化
オンプレミス環境で発生していた様々な見えないコストを大幅に削減できます。サーバの購入費や数年ごとの更新費用、保守契約料、データセンター利用料、サーバ管理者の人件費などが不要になり、月額、または年額のサービス利用料に一本化されます。
ある試算では、オンプレミスサーバの5年間の総所有コスト(TCO)と比較して、クラウドサービスを利用することで最大70%ものコスト削減につながるケースもあります。 削減できたコストを、企業の成長に直結するコア業務に再投資できます。
クラウドの安全性を基盤に、企業の競争力を強化する
クラウドの安全性はもはや守りのためだけのものではありません。企業の持続的な成長を支え、競争力強化に繋がる攻めの基盤となります。
事業継続性(BCP)の飛躍的向上
本社や営業所が災害に見舞われても、データは堅牢なデータセンターで保護されているため、インターネット環境さえあれば、別の場所からすぐに事業を再開できます。これは、企業の信頼性と事業継続性を担保する上で極めて重要です。クラウドを活用したBCP対策は、現代企業にとって必須の取り組みと言えるでしょう。
多様な働き方への対応と人材確保
安全なテレワーク環境は、育児や介護といった事情を抱える従業員も働き続けやすくするだけでなく、遠隔地に住む優秀な人材を採用するチャンスも広げます。これは、人材不足が深刻化する現代において大きな競争力となります。従業員が安心して働ける環境を提供することは、エンゲージメントの向上にも繋がります。
まとめ:クラウド活用は安全性が高い経営戦略
適切に設計・運用されている法人向けクラウドサービスは、自社でサーバを管理する以上に堅牢なセキュリティ環境を提供してくれます。そして、その高い安全性を基盤として、コスト削減、生産性向上、事業継続性の強化といった、企業の成長に不可欠な多くのメリットを享受することができます。
安全で効率的な情報共有基盤を構築することは、未来の企業競争力を左右する、重要な経営戦略なのです。まずは自社の課題を洗い出し、どのような機能が必要なのかを整理することから始めてみてはいかがでしょうか。